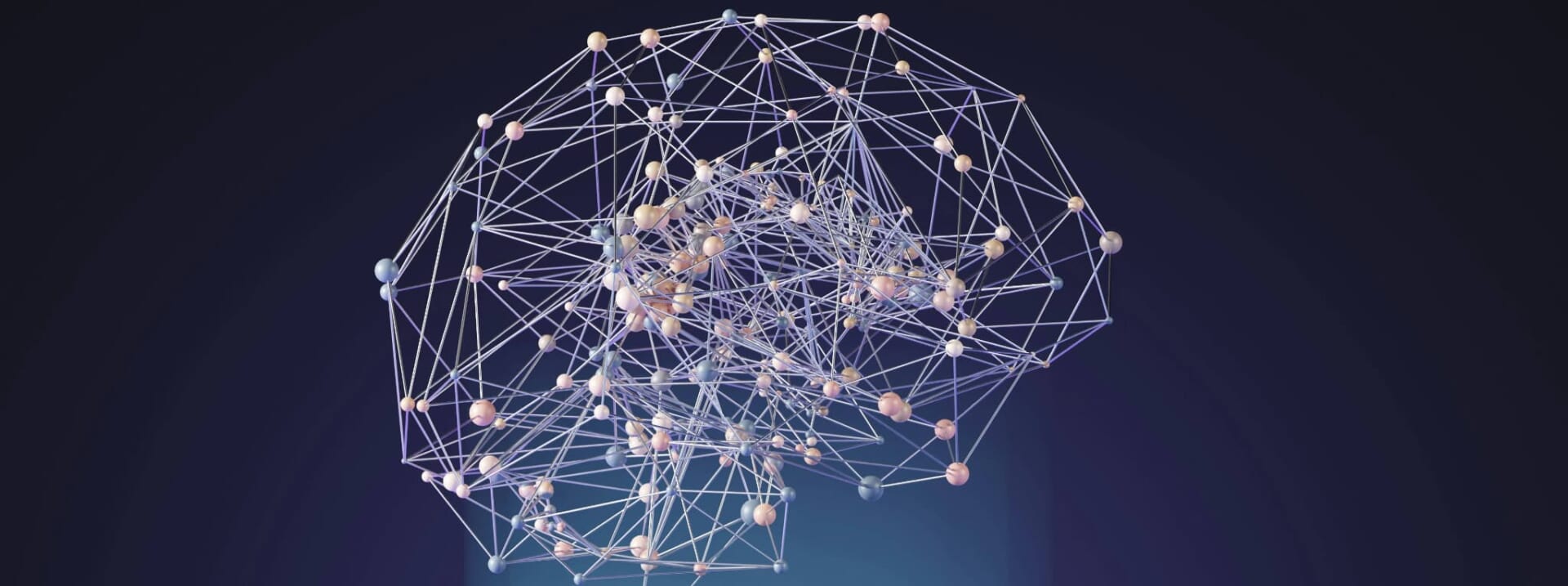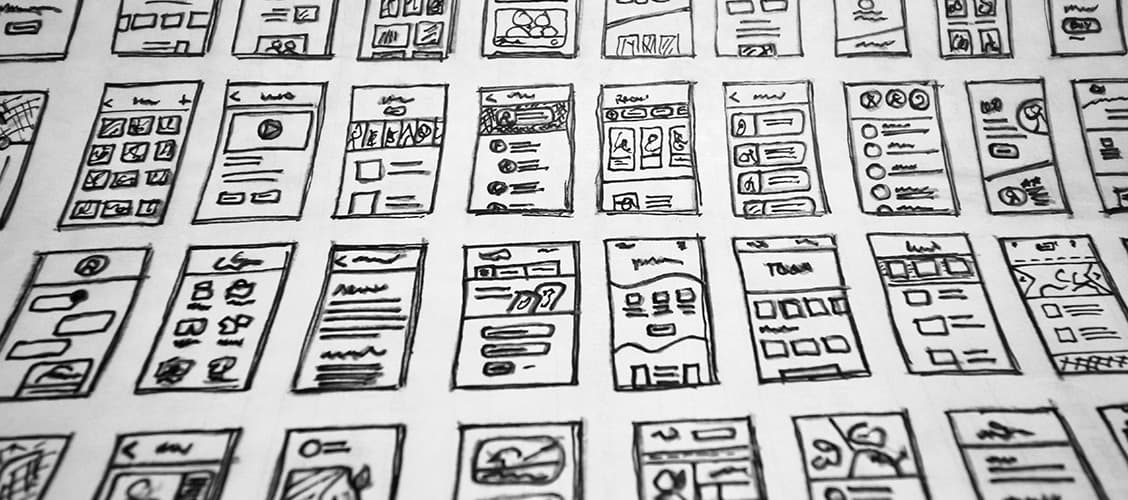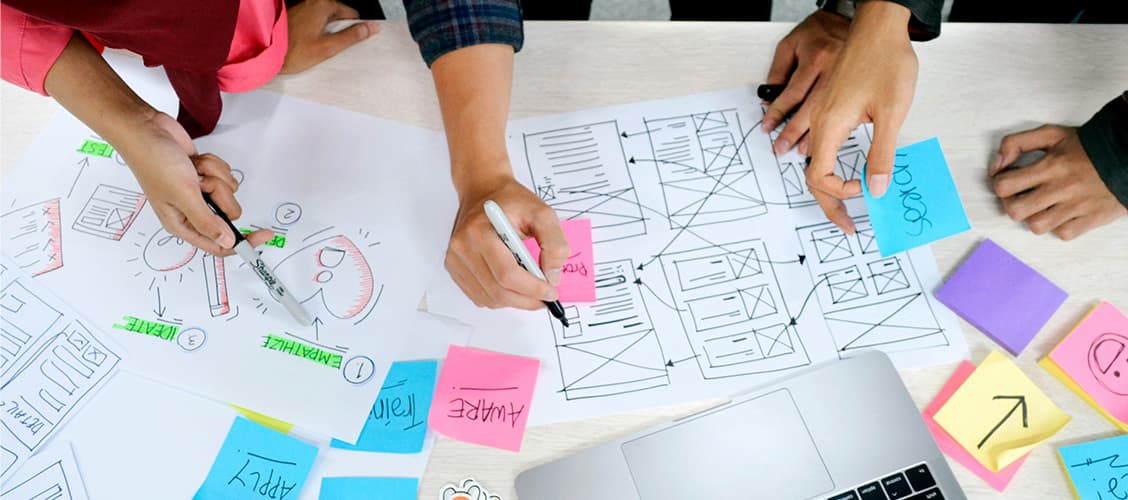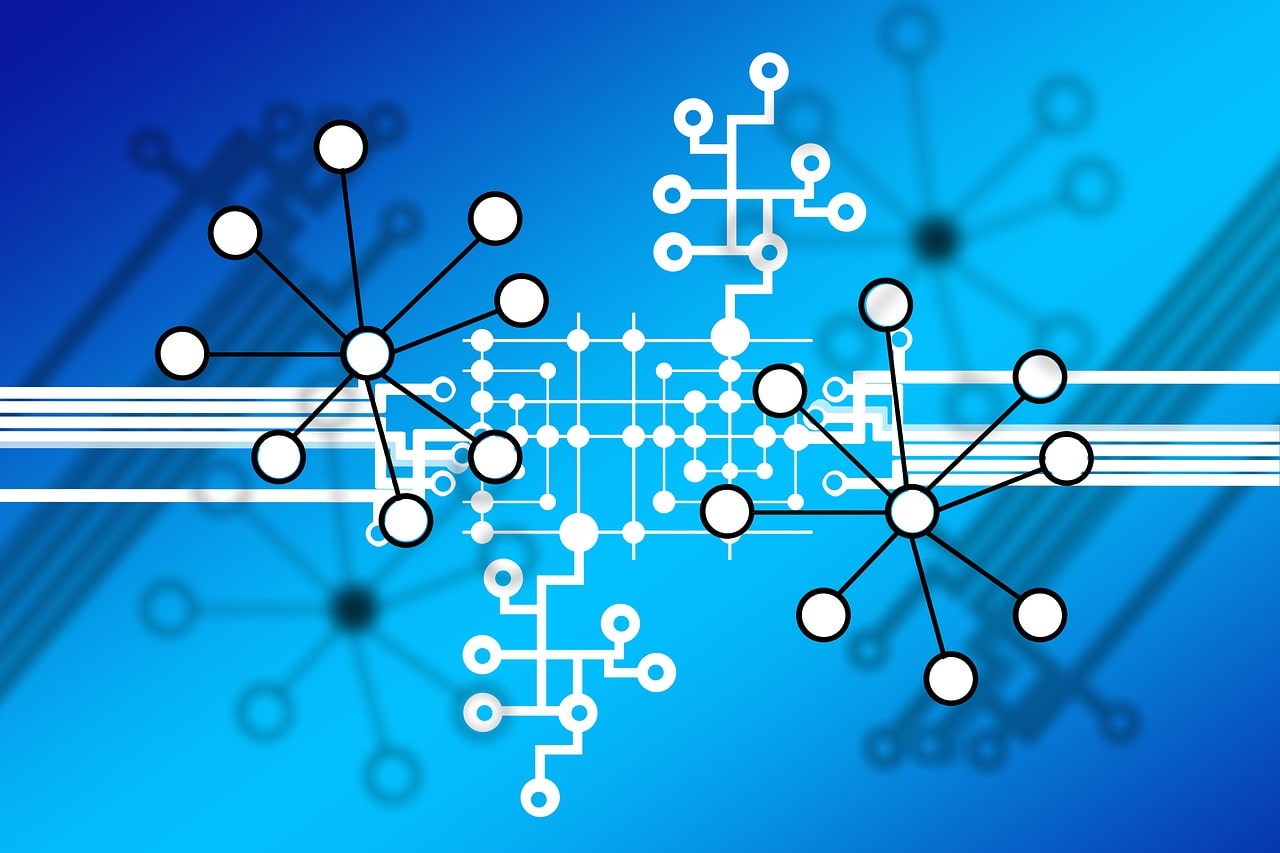UI/UXとSEOの関係性とは
UIとUXの基本的な意味と違い
UIとUXは、似ているようでまったく別の概念です。UIは「ユーザーインターフェース」の略で、ボタンやメニュー、文字サイズ、色使いなど、画面上で利用者が直接触れる部分を指します。たとえば、問い合わせボタンが分かりやすい位置にあるか、テキストが読みやすいかといった点がUIの領域です。
一方でUXは「ユーザーエクスペリエンス」、つまりサイトを利用したときに得られる全体的な体験を意味します。UIが「入り口や通路のデザイン」だとすれば、UXは「その建物を訪れたときの居心地や満足感」に近いものです。レストランを例にすれば、UIはメニューの見やすさや注文のしやすさ、UXは料理の味や店員の対応、居心地の良さを含めた“体験全体”と言えるでしょう。
この二つは切り離せない関係にあります。UIが整っていても、体験としてのUXが悪ければユーザーは離れてしまいますし、その逆も同じです。SEOを考えるうえでは、このUIとUXを一体のものとして捉えることが重要になります。
SEOの基本と評価要因
SEOとは「検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)」のことです。検索結果で上位に表示されることで、見込み顧客のアクセスを増やし、ビジネスの成果につなげる取り組みを指します。
Googleは200以上の評価要因をもとに検索順位を決めているとされます。その中でも近年特に重視されているのが「ユーザーの行動データ」です。例えば、ページに訪れた人がすぐに離脱するか、どれくらい滞在するか、他のページにも回遊するかなど、利用者の行動が評価に直結します。
つまり単にキーワードを盛り込むだけでは不十分です。ユーザーが快適に情報を得られるサイト設計がされていなければ、検索エンジンからの評価は高まりません。SEOはテクニックの積み重ねだけでなく、「人が心地よく利用できるかどうか」という視点が欠かせないのです。
なぜUI/UXがSEOに影響を与えるのか
では、なぜUIやUXがSEOに影響するのでしょうか。その背景には「検索エンジンの進化」があります。かつてはリンクの数やキーワードの出現率といった技術的な要素が中心でしたが、今ではユーザー体験そのものが検索エンジンによる評価対象になっています。
例えば、ページを開くのに時間がかかると、多くの人は数秒で離脱します。これは直帰率の上昇につながり、Googleから「ユーザー満足度が低いサイト」と判断されてしまいます。逆に、スムーズに操作できて情報が整理されていれば、ユーザーは長く滞在し、複数ページを回遊します。結果として評価が高まり、順位が上がるのです。
これは日常生活に置き換えると分かりやすいかもしれません。例えば、駅前に二つのカフェがあったとして、一方は注文から提供までがスムーズで座席も快適、もう一方は注文に時間がかかり席も狭いとしたら、どちらを選ぶでしょうか。多くの人が前者に集まるのと同じように、Webサイトでも体験の良し悪しが利用者の行動を左右し、それが検索順位に跳ね返るのです。
要するに、SEOはもはや「検索エンジンだけを意識した対策」ではなく、「UI/UX改善を通じてユーザーの満足度を高める取り組み」と表裏一体のものになっているのです。
併せて読みたい:優れたUIの10の特徴 UXとの違い 実現のポイントも解説
SEOに影響を与える主要なUI/UX指標
直帰率と滞在時間
直帰率とは、訪問者が最初に開いたページだけを見て離脱してしまう割合のことです。もし直帰率が高ければ、ユーザーが「欲しい情報がすぐに得られなかった」可能性があります。たとえば、商品ページを開いたのに説明が不十分だったり、CTAボタンがわかりにくかったりすると、次の行動に進まずに閉じてしまうのです。
一方で滞在時間は、ユーザーがページにどれだけ長く留まったかを示します。文章の分かりやすさや画像の見やすさ、さらにはストーリー性のある構成は、自然と滞在時間を延ばす効果があります。実際、滞在時間が長いページは「有益な情報が提供されている」と評価され、検索順位が向上しやすくなります。
ページの表示速度とCore Web Vitals
ページの表示速度は、数秒遅れるだけで離脱率を大きく上げる要因になります。Googleが導入している「Core Web Vitals」では、特に以下の3つの指標が重視されています。
- LCP(Largest Contentful Paint):メインコンテンツが表示されるまでの時間
- FID(First Input Delay):クリックや入力が反応するまでの速さ
- CLS(Cumulative Layout Shift):画面がどれだけ安定して表示されるか
これらは単なる技術的な数値ではなく、ユーザー体験そのものに直結します。例えば、ボタンを押したのに数秒間反応がないと、多くの人は苛立ちを感じ、離脱してしまうでしょう。表示速度を改善することは、SEOに直結するだけでなく、ユーザーにストレスを与えない信頼性の高いサイト運営につながります。
モバイルフレンドリーとレスポンシブ対応
現在のWeb利用の大半はスマートフォンから行われています。そのため、モバイルで快適に閲覧できるかどうかはSEOに直結するポイントです。文字が小さすぎて読みにくい、ボタンが押しにくい、横スクロールが必要といったサイトは、ユーザーに「使いづらい」と感じさせてしまいます。
レスポンシブデザインを導入し、どのデバイスでもレイアウトが最適化されるようにすることは必須です。モバイルユーザーが快適に操作できることで、滞在時間やエンゲージメントが自然と高まり、検索順位にも良い影響を与えます。
エンゲージメント率やセッション指標
単にアクセス数が多いだけでは、サイトの価値は測れません。重要なのは「どれだけ深く関わってもらえたか」です。エンゲージメント率やセッション数は、ユーザーが複数ページを閲覧したり、資料請求やお問い合わせといった行動に至ったかを示す大切な指標です。
例えば、ブログ記事を読んだあとにサービスページを回遊し、最終的に問い合わせまで進んだとすれば、そのユーザー体験は非常に良好だったと言えます。こうした行動が積み重なることで、検索エンジンからの評価も高まり、持続的に順位が安定していきます。
あわせて読みたい:ユーザー体験を高めるUXの重要性について
SEO効果を高めるUI/UX改善方法

SEOの成果を最大化するには、ユーザーの行動を前提にしたUI/UXの改善が欠かせません。単に検索順位を上げるだけではなく、訪問者が「このサイトは使いやすい」「また見たい」と感じることで初めて成果につながります。ここでは、特に効果的な改善のポイントを紹介します。
情報設計とナビゲーションの最適化
情報設計とは、ユーザーが求める情報に迷わずたどり着けるようにコンテンツを整理することです。ナビゲーションが複雑だったり、カテゴリがわかりにくいと、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。
例えば、よくある失敗として「サービス紹介」と「料金案内」が別の階層に埋もれているケースがあります。ユーザーは「すぐに料金が知りたい」と思っているのに、数回クリックしないと見つからない。こうした構造は、直帰率の増加やコンバージョン率の低下につながります。
最適化のポイントは「最短3クリックで目的の情報にたどり着ける」こと。サイトマップやパンくずリストを活用するのも有効です。
見出し・文字サイズ・行間の調整による可読性向上
検索エンジンはテキストを重視しますが、ユーザーにとっても読みやすさは大切です。文字が小さすぎたり行間が詰まりすぎていると、内容が頭に入ってこず、読む前に閉じてしまう人も少なくありません。
特にビジネスサイトでは、役員や経営層といった「時間に余裕のない層」も読者となります。文章を素早く理解できるよう、見出しは適度に配置し、本文はフォントサイズや行間を調整して視認性を高めましょう。紙の書籍と同じで、読みやすいレイアウトは記憶に残りやすく、滞在時間を伸ばす効果があります。
関連リンク・内部リンクの設置
関連リンクや内部リンクは、ユーザーの回遊を促すと同時にSEOにも効果的です。1つの記事を読んだあとに「関連するサービスページ」や「詳しい解説記事」にスムーズに誘導できれば、滞在時間も増え、サイト全体の評価が高まります。
例えば、ある企業の導入事例を紹介する記事から「サービス詳細ページ」へリンクすることで、興味を持った読者を自然に次の行動へ導けます。内部リンクは、単なるSEO対策ではなく「ユーザーの学習や検討の流れをサポートする道しるべ」として設計するのが理想です。
アクセシビリティとユーザビリティの確保
近年、アクセシビリティの重要性は高まっています。高齢者や障がいのあるユーザーでも利用しやすい設計を行うことは、企業の社会的信頼を高めるだけでなく、結果的にSEOにも寄与します。
たとえば、画像に代替テキストを設定すれば、スクリーンリーダーで内容を理解できますし、検索エンジンのクロール精度も向上します。また、ボタンのタップ領域を広げると、モバイルユーザーが誤操作せずに行動できるため、コンバージョン率改善にも直結します。
アクセシビリティは「すべての人にやさしい設計」であり、その積み重ねが結果としてSEOに強いサイトをつくるのです。
デザイン要素(画像・ボタン・配置)の改善
最後に、デザイン要素そのものもSEOに影響します。画像が大きすぎて表示が遅い、ボタンの色や配置がわかりにくい、といった細部は、ユーザー体験を損なう大きな要因です。
例えば、資料請求ボタンが画面下部に隠れていたら、多くの人は気づかずに離脱してしまいます。逆に、適切な位置に強調したボタンを配置すれば、次の行動につながりやすくなります。
また、画像は圧縮して軽量化しつつ、高解像度で見やすさを保つ工夫が必要です。細部の調整こそが「使いやすいサイト」を支え、SEOにおける成果へとつながっていきます。
経営層が押さえるべきUI/UX改善の戦略視点
成果に直結するKPIの設定とモニタリング
改善の効果を測るには、具体的なKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。単に「検索順位を上げる」ではなく、問い合わせ件数や資料請求数、コンバージョン率など、ビジネスの成果に直結する指標を選ぶことが大切です。
例えば、ある企業では「直帰率を10%改善」「平均滞在時間を30秒延長」といった数値目標を定め、改善の進捗を定期的にモニタリングしました。その結果、サイトの集客力だけでなく商談化率の向上にもつながったのです。KPIを経営層が把握することで、現場の取り組みが「数字で語れる成果」に結びつきやすくなります。
ROIを意識したUI/UX改善の投資判断
UI/UX改善にはコストがかかります。しかし、「費用が発生する=コスト」ではなく、「改善によって得られる利益=投資」と捉えるべきです。ROI(投資対効果)を意識することで、施策に優先順位をつけられます。
例えば、ページの表示速度を改善するためのサーバー増強は、初期投資が必要ですが、直帰率低下や売上増加に直結する可能性があります。経営層がROIを踏まえて判断することで、「予算をどこに配分すべきか」が明確になり、現場の動きもスムーズになります。
データ分析と改善サイクルの構築
一度UI/UXを改善したからといって、その効果が永続するわけではありません。ユーザーの行動は市場環境や時代背景によって変化します。したがって、定期的なデータ分析と改善サイクルの構築が重要です。
例えば、Googleアナリティクスやヒートマップツールを使えば、ユーザーがどの部分で離脱しているのか、どのリンクがクリックされているのかを把握できます。そのデータをもとに仮説を立て、小規模な改善を繰り返すことで、大規模なリニューアル以上の成果を出せることもあります。
SEOとUI/UXの統合的な運用戦略
SEOとUI/UXを別々に考えてしまうと、どうしても施策が断片的になりがちです。重要なのは「統合的な運用戦略」を描くことです。
例えば、新しいコンテンツを作成するときにSEOを意識するのは当然ですが、その段階からUI設計やUX改善も同時に検討すれば、公開直後からユーザー体験と検索順位の双方に良い影響を与えられます。
経営層がこの統合視点を持つことで、単なる「アクセス数の増加」ではなく、「売上やブランド価値を高めるWebサイト運営」へと発展させることが可能になります。
併せて読みたい:Webサイト改善で成果を最大化する方法|UIUX・SEO・分析ツール活用術
成功事例に学ぶUI/UX改善とSEO効果

理論や指標を理解しても、「実際に成果が出るのか」という疑問を抱く方は少なくありません。ここでは、UI/UXデザインとSEOの両面に豊富な知見と実績を持つサックルが改善を担った具体的な事例を紹介します。単なる順位上昇だけでなく、ビジネス成果に直結する効果をどのように生み出したのかを見ていきましょう。
ECサイトでの直帰率低下と売上増加
ある大手ECサイトでは、直帰率が高く、広告で集客しても売上につながらないという課題がありました。サックルはまずUI面での商品検索導線を改善し、UXの観点から「おすすめ商品」や「レビュー表示」を強化。結果として、直帰率は20%以上改善し、平均注文単価も上昇しました。SEOの流入増加と併せて、売上全体が前年対比で大幅に伸びる成果を実現しました。
コーポレートサイトのUI刷新による検索順位改善
あるBtoB企業のコーポレートサイトは、見た目は整っていても情報が探しにくく、検索順位も伸び悩んでいました。サックルはUIを全面的に刷新し、ナビゲーションの整理やレスポンシブ対応を強化。UX面では、企業理念やサービス内容をストーリー性を持たせて訴求することで滞在時間を延ばし、検索順位も複数の主要キーワードで上位を獲得。問い合わせ件数が倍増するという成果につながりました。
サービスサイトにおけるユーザー満足度向上
新規サービスを展開する企業のWebサイトでは、利用者から「情報が分かりにくい」「操作が煩雑」という声が多く、リピート率の改善が課題となっていました。サックルはUXリサーチをもとに情報設計を見直し、ボタン配置やフォーム入力の負担を軽減。さらにSEOを意識したコンテンツ最適化も同時に行った結果、検索流入が増加しただけでなく、アンケートでの満足度が大きく改善しました。結果として、顧客の定着率が向上し、サービス全体の成長を後押ししました。
まとめ
本記事では、UIとUXの基本的な違いからSEOとの関係、具体的な改善方法や経営層が押さえるべき戦略的視点、さらに実際の成功事例までを解説しました。いずれの事例も共通していたのは、「ユーザーの視点を第一に考えたデザイン改善」が成果を生み出していたことです。
もし自社のWebサイトに課題を感じているなら、UI/UX改善とSEOを切り離して考えるのではなく、統合的に取り組むことをおすすめします。サックルは、サイトやアプリの制作・改善において、UI/UXデザインとSEOの双方に強みを持っています。成果に直結する改善を実現したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。